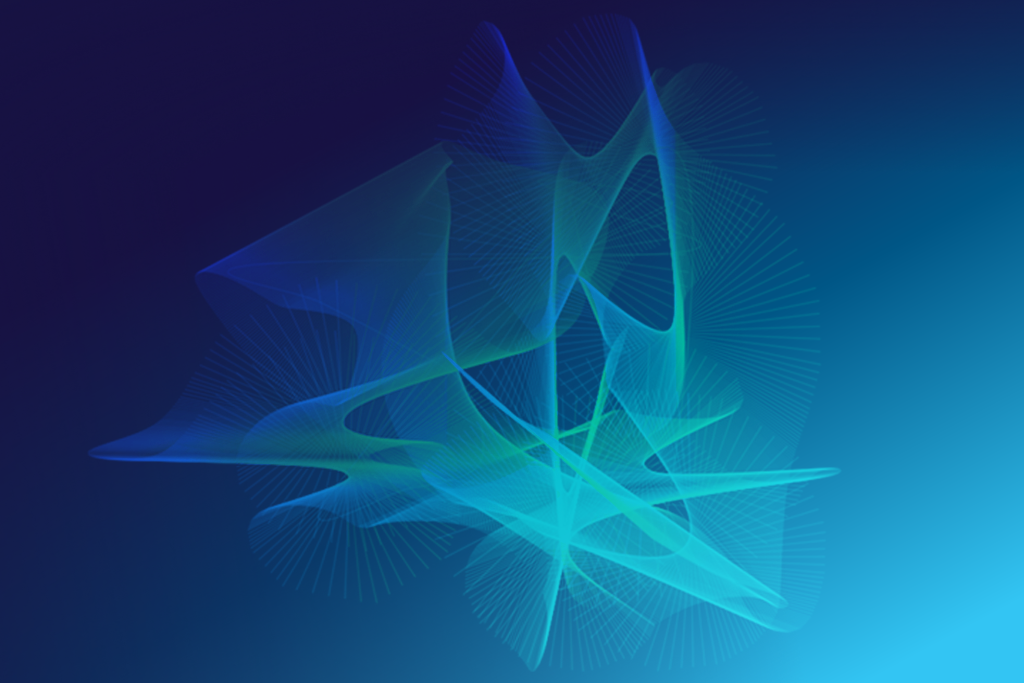近年、"デジタルヘルス"という言葉は医療・製薬業界で広く浸透していますが、その進化の過程は目まぐるしく、過去10年で投資・開発・期待・実装の形が大きく変化してきました。 IQVIA INSTITUTEでは2017年に初の分析レポート「The Growing Value of Digital Health」を発表し、2021年に「Digital Health Trends 2021」、そして2024年には最新版「Digital Health Trends 2024」をリリースしました。
IQVIAジャパンのマネジメントコンサルティングでは「日本におけるDTx市場展望」として、この最新レポートの内容とともに、国内における現状を分析のうえ、製薬業界におけるインパクトや今後のシナリオを考察しており、以下にそのサマリを紹介します。
世界のデジタルヘルス動向
(オリモト・クリス・カズナリ プリンシパル)
デジタルヘルスとは
健康増進アプリや服薬管理アプリ等、大枠として「デジタルヘルス」という広範な健康関連ソリューションの中に、AI画像診断等の「デジタルメディスン(プログラム医療機器;SaMD)」があり、さらにその一部として疾患等の予防・管理・治療のため、エビデンスに基づいて治療的介入をする治療用アプリ等の「デジタルセラピューティクス(DTx)」が存在する。「デジタルヘルス」の中には薬事承認の必要がないものもあるが、「SaMD」と「DTx」には薬事承認が必要である。
加速するデジタルヘルス関連市場
デジタルヘルスの世界的な推進要因は以下による。
- 社会的背景=高齢化に伴う医療費の増大、非効率的な医療業務体制、地域医療格差
- 技術の進歩=AI 技術の発達による問診・画像診断の精度向上、5G・ロボット技術の発達による遠隔診療の向上、VR技術の発達による治療サポート機器の出現
こうした背景の中、デジタルヘルスが大きく注目される理由として、①未病から経過観察のすべての段階でソリューション展開が可能、 ②患者個人に限らず複数のステークホルダーに同時アプローチが可能という2点の特徴が挙げられる。セルフケア、診断、治療、モニタリングの各ステップにデジタルヘルスが関与することで患者のアウトカムを向上させる可能性に期待が寄せられている。
デジタルヘルスソリューションの供給者はライフサイエンス企業、規制当局、医療提供者、患者など、エコシステムの全利害関係者に対して価値創出する必要がある。また、各国で規制や償還制度、プロバイダーとの連携、患者のニーズなどが異なるという現状ゆえに、製薬企業とのパートナーシップや投資の重要性にも注目が集まっている。
デジタルヘルスapp(アプリ)の実態
GooglePlayによれば、一般消費者向けデジタルヘルス関連アプリは2013年時点で6万6713件だったが、2021年頃にピークを迎え全世界で約36万件リリースされている。その後、リリース数そのものは減少しているが、年々アプリで取り扱うカテゴリがヘルス・ウェルネスから疾患治療・管理が主目的の疾患特化型へと変化してきたことによると考えられる。また、疾患・領域別ではメンタルヘルス(精神疾患)が25%で最も多く、次いで糖尿病14%、心疾患12%、消化器系6%、がん6%と続く。
こうしたデジタルヘルスのアプリの成功要因として、ユーザーの評価や利用率、リテンションレート(定着率)の重要性がある。現在最も多くインストールされているMyFitnessPal、BetterMeなどのデジタルヘルスアプリは、科学的根拠、開発者に対する拡張性、機能、学術的なアウトカム、ユーザーの評価などが総じて高くなっている。
デジタルヘルスTechの活用方法
デジタルヘルステクノロジーの収集データは、デジタルバイオマーカー(客観的・定量的に収集・測定される生体データ)としてプレスクリーニング、診断、モニタリング、疾患の進行予測から治療まで幅広くサポートすることができる。
ウェアラブルデバイスやモバイルデバイス、医療デバイスによって測定されるデジタルバイオマーカーの具体例としては、体の動き、身体組成、イメージ分析、スピーチ・言語の分析、眼球の動き、睡眠パターンなどが挙げられ、またセンサーやAI/ML(機械学習)の発達に伴い、精度の向上も目覚ましい。
各国におけるデジタルセラピューティクス(DTx)の現状
承認済の処方箋DTx(PDTx)は、2021年から2024年の間に世界全体で25製品から140製品と5倍以上に増加している。なかでも精神・中枢神経系疾患を対象とした製品が多く、内訳は精神疾患40%、中枢神経系疾患(CNS)22%となっている。
一方、承認済DTxは世界全体で150製品を超えており、特にドイツ、アメリカ、イギリスでの承認、市場投入が進んでいる。日本は現状、承認数で大幅な遅れをとっている。
- ドイツ<65製品>:精神疾患(47%)、内分泌/代謝系疾患(12%)、整形外科・疼痛(12%) 特徴:Fast Track制度による迅速承認(申請から最短3カ月以内に保険償還、治験の比較対象群としてリアルワールドデータ(RWD)使用可、メーカー側での保険償還1年目の価格設定可)
- アメリカ<62製品>:心血管疾患(39%)、呼吸器疾患(21%)、神経系/精神疾患(18%) 特徴:SaMDに関する制度の精力的な設計・フォーミュラリ作成(研究開発に関する制度整備だけでなく、フォーミュラリ作成等による保険償還・アクセス性向上を図っている)
- イギリス<29製品>:精神疾患、整形外科・疼痛、呼吸器系 特徴:開発/評価指針策定による実行性向上(有効性だけでなく、経済的インパクトや利便性、データ利用に関する倫理原則等を定めた複数の指針を発表)
DTx承認数上位3カ国のドイツ、アメリカ、イギリスでは制度が成熟しており、特にドイツではDTxの申請プロセスと評価フレームワークが公式に確立されている。アメリカでは個別の公式プロセスはないものの、アドホックなプロセスを経て承認されており、イギリスでもドイツに近い制度によってDTxに特化したプロセスと保険償還パスが存在するなど、DTx開発推進のため、開発側にメリットのある制度等の構築が進んでいる。
また、アジアにおける動向としては、韓国<4製品>やシンガポール<1製品>、オーストラリアでもDTx導入に向けた制度整備が加速している。
日本におけるDTxの現状と課題
(加藤雄志 マネージャー)
日本におけるPDTx関連制度や承認・開発状況
日本では、DTxは「プログラム医療機器」に分類されており、プログラム医療機器としての該当性・クラス分類、先駆的・特定用途医療機器としての指定制度による優先審査、条件付き承認制度、変更計画確認手続制度(IDATEN制度)などの制度に則って開発が進められている。
- プログラム医療機器:医療機器のうちプログラム(電子計算機に対する指令であって、―の結果を得ることができるように組み合わされたもの)及びこれを記録した記録媒体のこと。
- 先駆的医療機器:世界に先駆けて開発され、早期の治験段階で著明な有効性が見込まれるニーズの高い医療機器等を指定し、各種支援による早期の実用化を目指す「先駆け審査指定制度」を法制化。
- 特定用途医療機器:小児の疾病に用いる医療機器等、医療上のニーズが著しく充足されていない医療機器等について、「特定用途医療機器」等として指定。
- 条件付き承認制度:重篤で有効な治療方法に乏しい疾患の医療機器で、一定の臨床データはあるが、患者数が少ない等の理由で新たな臨床試験の実施が困難な場合、製造販売後のリスク管理措置を実施すること等を条件として、必要性の高い医療機器への速やかな患者アクセスの確保を図る制度。
- 変更計画確認手続制度(IDATEN制度):改良が見込まれている医療機器について、変更計画を審査の過程で確認し、計画された範囲の中で迅速な承認事項の一部変更を認めることにより、継続した改良を可能とする承認審査制度を導入。 市販後に恒常的な性能等が変化する医療機器について、医療機器の改善・改良プロセスを評価することにより、市販後の性能変化に併せて柔軟に承認内容を変更可能とする方策を踏まえた承認審査を実現。
しかし、2025年4月時点での承認済みPDTx製品はわずか5製品(CureApp SC、CureApp HT、サスメド Med CBT-I 不眠障害用アプリ、CureApp AUD、ENDEAVORRIDE)である。開発中のDTx製品は製薬企業やDTx企業だけでなく、医療機関や大学も参画したものが10製品以上あるものの、各国と比較して非常に少ない。
DTx製品の開発が少ない要因として、「制度の未熟さ」と「収益性の不透明さ」が挙げられる。
「制度の未熟さ」におけるもっとも大きな問題は、開発~保険償還までのすべての段階で評価基準が不明瞭なことである。開発段階では医療機器への該当性判断が難しく、薬事承認段階では承認の評価基準が不明瞭である。保険償還段階では償還基準が不明瞭であり、薬事承認されても保険償還されない場合が見受けられる。そのほかにも、開発段階での個人情報の取扱いの煩雑さや、良質かつ十分な医療データの収集の難しさ、薬事承認段階での承認審査期間の長さや見通しの立ちづらさといった問題を抱えている。
「収益性の不透明さ」においては、保険償還の有無によらず、ビジネスモデルが確立されていないことが開発の足枷となっている。また、保険償還されたとしても、償還基準が不明瞭で想定より低い価格を設定される場合がある点や、患者側のPDTxへの認知度が低く導入が進まないことから収益が想定に満たない点も指摘したい。
日本におけるPDTx普及、浸透に向けた取り組み
開発数などで各国に遅れをとってはいるが、近年、日本でもヘルスケアスタートアップの資金調達やヘルスケア領域への投資が増加しており、PDTxの浸透加速にも寄与すると考えられる。経済産業省によれば、2017年時のヘルスケアスタートアップの資金調達は約40社・約150億円だったが、2021年には約160社・約700億円の資金調達に成功している。また、日本のベンチャーキャピタルからヘルスケア領域への投資状況も約1500件・約2600億円と、約1300件・約1300億円だった2017年時と比較すると投資金額は倍増している。
具体事例としては、2022年にグローバル投資会社であるCARLYLEと日本のMedTechベンチャーであるCureAppが戦略的パートナーシップを提携し、約70億円の出資を受け日本初の薬事承認取得アプリを開発した。
また、2023年には経産省もヘルスケアスタートアップのエコシステム強化事業に23億円の補正予算を組むなど、国のバックアップ体制も進んでいる。
PDTx普及の課題
PDTxの普及には、前述のとおり、薬事承認や保険償還制度などの整備、収益モデルの確立、患者のPDTxへの理解促進や啓発といった課題解決が重要となる。また、保険償還を前提とした製品開発では、「患者導入ハードルの低い疾患の選定」と「保険償還され高い点数が設定される製品設計」が重要である。
「患者導入ハードルの低い疾患の選定」では、患者が現治療+αでお金を支払っても良いと価値を見出せる疾患(現治療のみでは効果不十分、もしくは自己管理が難しい生活困難度の高い疾患など)の選定が重要であるとともに、PDTxの特性を踏まえた疾患選定も重要である。
- PDTxの特徴①:治療の「空白」を埋められる
医師による診療がない期間、つまり治療の空白期間は、通常患者へのフォローを十分に行えない。PDTxを活用することで、日々の状態をデータとして収集でき、経過分析しやすくなるため、治療の空白を埋めやすくなる - PDTxの特徴②:医療上の多様なニーズに対応できる
有効な医薬品や治療法が少ない疾患に対しても、PDTxで対応することが可能(がん患者のQOL改善、うつ病患者のケアなど)。また、医薬品だけでは症状が改善しにくい疾患において、現治療とPDTxを併用することで効果を高めることも可能(生活習慣病など)
これらのPDTxの特徴から、精神疾患や生活習慣病、がんなどの疾患にて大きく価値提供できると期待されている。
国内PDTx市場規模予測
制度整備が進めば2030年には最大100億円
2025年、国内PDTx市場規模は10億円程度と見込まれる。
現状のままの成長が続けば、2030年には以下となる。
- ベースケース:30〜35億円
2028年に制度変更がなく、現在の上市アプリのダウンロード数と各対象疾患の診断者数をもとに算出
しかし今後、承認スピードや保険点数の見直し等の制度整備が十分に行われた場合、たとえば2028年に制度変更があると仮定すると、以下の2つのケースが想定される。
- ミドルケース:50〜60億円
2028年より制度変更(成長率変更)を適用。上市品の想定ピーク処方数と各疾患の診断患者数をもとに算出 - ベストケース:80〜100億円
2028年より制度変更(成長率変更)を適用。デジタルヘルスアプリダウンロード率とPDTx遵守率により想定ピーク処方数を拡大。その他算出はミドルケースと同様
あくまでも今後の制度整備次第の予測ではあるが、世界中で加速しているAIやMLを含むヘルスケア領域のデジタル化は急速に日本にも押し寄せてきており、日本におけるPDTx市場の規模拡大は必至。
一方、ヘルスケア領域のデジタル化に対する考え方が進歩しなければ、PDTx製品の開発の遅れを招き、ドラッグラグ・ロスと同様の状況になる懸念がある。
また、ヘルスケア領域のデジタル化に対する考え方の遅れは、RWDの蓄積の遅れと、それに伴うRWD/RWEを活用した臨床試験の遅れにつながり、結果として医療用医薬品のドラッグラグ・ロスが拡大する可能性も懸念される
まとめ
昨今世界中で加熱しているデジタルヘルスやDTxについて、欧米を中心に制度整備が進められ、多くの製品が開発・上市されている。一方日本では、制度整備は進められてはいるものの、制度の未熟さやビジネスとしての収益の不透明さから上市品・開発品ともに少ないのが現状である。ヘルスケアスタートアップへの投資や国のバックアップに加え、制度面・収益面の改善は急務であり、また併せて患者・医療従事者双方の理解推進も重要である。